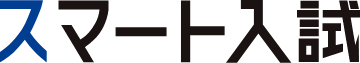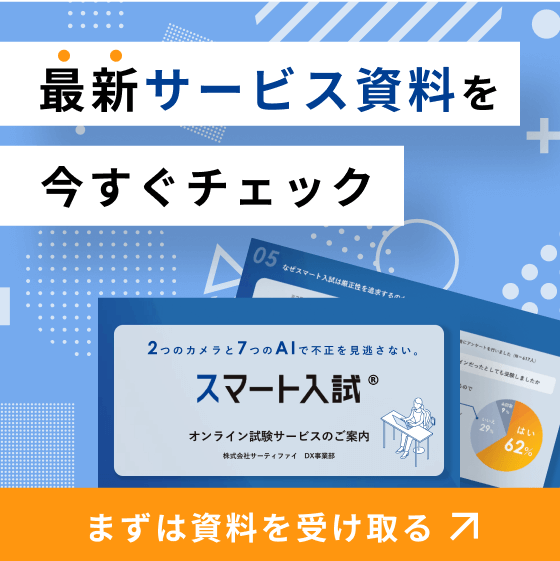CBT試験とは?IBTとの違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

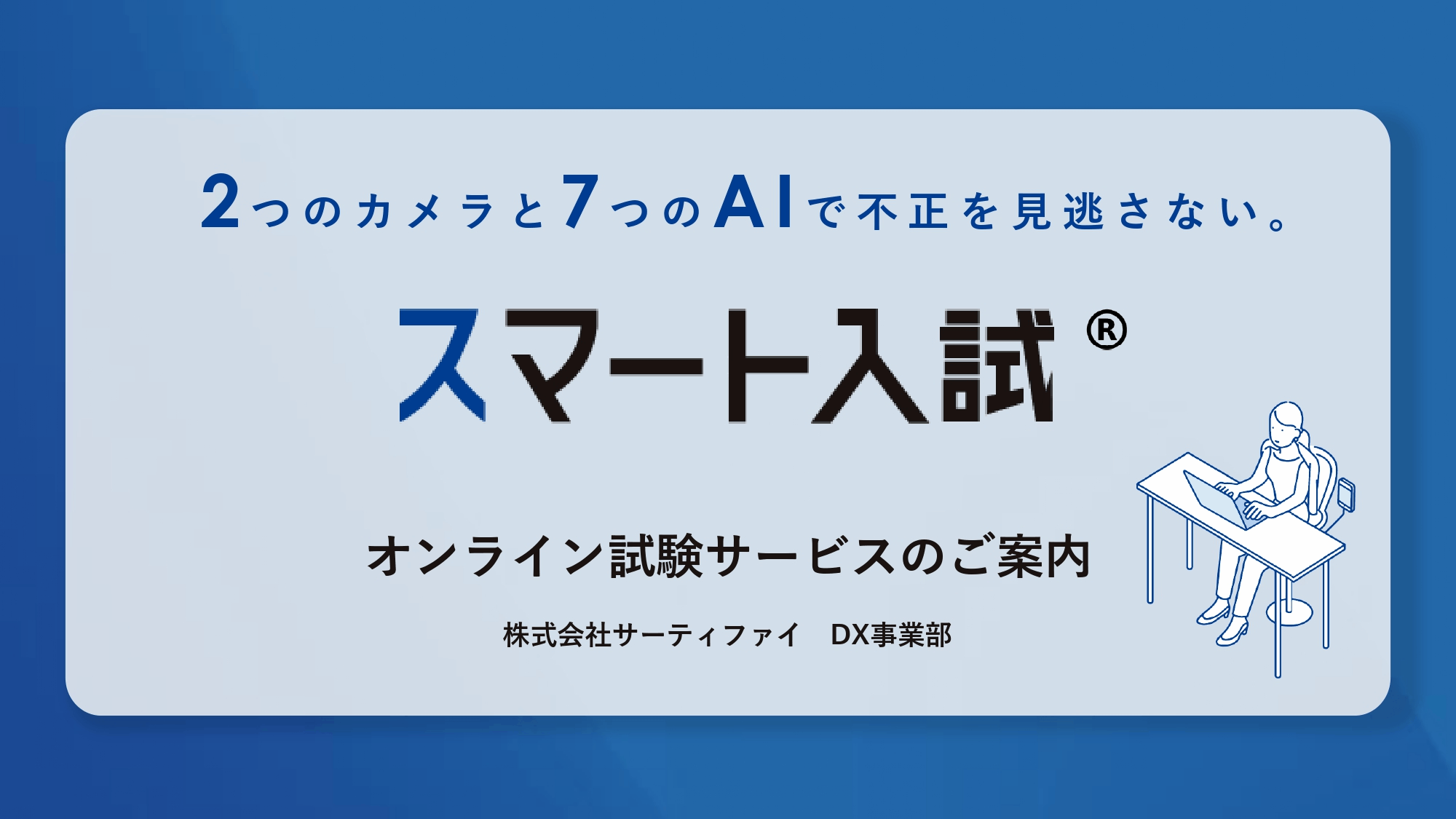
6分でわかる! オンライン試験サービス「スマート入試」紹介資料
スマート入試はPCカメラの他にスマートフォンのカメラを第二のカメラとして活用し、7つのAIを駆使することで不正抑止効果を飛躍的に高めたオンライン試験システム/不正監視システムです。 スマート入試のサービスの概要や料金プランを知りたい方は、まずこちらの資料をご覧ください。
CBTとは
CBTとは、コンピューターを利用して行う試験の方式です。受験者が試験会場へ行き、設置されているコンピューターを使用して受験します。CBTは「Computer Based Testing」の頭文字をとった表現です。CBT方式やCBT試験などともよばれますが、基本的には同じ試験の方法を示しています。
なお、従来の用紙に書き込む試験は、CBTに対して「PBT(Paper Based Testing)」と表現される場合もあります。
IBTとの違い
IBTとは、受験者自身のパソコンを使って実施する試験の方式です。「Internet Based Testing」を略してIBTとよんでいます。なかにはタブレットやスマートフォンに対応している試験もあり、場所を問わずどこからでも受験可能です。
なお、CBTを「テストセンター型」、IBTを「自宅型」とし、IBTもCBTに含める場合もあります。この記事では、テストセンター型をCBTとして解説しています。
PBTとの違い
PBT(Paper Based Testing)とは、紙と鉛筆を使って行う、従来からの試験方式で、多くの大学入試や資格試験などで採用されてきました。
PBTでは試験監督が直接監視するため、不正対策がしやすいというメリットがあります。
一方、受験会場の確保や紙の印刷・配布、採点作業に多大な時間とコストがかかります。 また、受験日や場所が限定されるため、受験機会が限られるというデメリットがあります。
試験センター・業務フローのデジタル化
試験センターでは、運営の効率化と品質向上のために、デジタル化が進められています。 PBTでは、問題用紙の印刷・配送、会場手配、採点・集計作業など、多くのコストと手間が発生します。
これらの業務をデジタル化することで、物理的なコストや人件費を大幅に削減できるのです。
また、デジタル化により、受験者にとっても利便性や公平性の向上といったメリットが生まれます。
CBT試験の特徴
CBTは、受験の申し込み、試験の実施、合否通知のすべてのプロセスをインターネットで完結できます。そのため、たとえば、感染症への対策が必要な状況でも「密」を避けて試験を実施できます。
スピーキング問題にも対応可能
CBTはインターネットやパソコンで実施し、基本的にはマウスやキーボードを使用して解答します。ただし、筆記や択一式の問題だけでなく、スピーキングの問題にも対応可能です。スピーキングの問題についてはヘッドセットで音声を聞き、マイクに音声を吹き込んで解答できます。
CBT試験が注目される背景
CBTに注目が集まった背景には、2020年の新型コロナウイルスの流行があります。多くの人が同じ場所に集まることが難しくなり、企業ではテレワーク、教育機関ではオンライン授業の導入が進みました。それに伴い、文部科学省をはじめとする政府機関は、CBTの導入を推進しています。また、CBTにはさまざまなメリットがあるため、導入を積極的に進めている企業も増えています。

CBT試験のメリット
CBTにはさまざまなメリットがあります。ここでは、CBTのメリットを解説します。
主催者にとってのメリット
まずは、主催者にとってのメリットです。
コストや手間を省いて試験実施できる
CBTは、従来の試験方式と比較してコストや手間を削減できるというメリットがあります。用紙を使用して試験を行うには、試験前から試験後の各プロセスで多くのコストや手間がかかります。具体的には、問題用紙や解答用紙の印刷、保管、配送、回収、廃棄などのプロセスがあり、それぞれ対応しなければなりません。
それに対してCBTは、試験に関するすべてのプロセスをインターネット上で完結させられます。コストや手間を抑え、スムーズな試験の実施が可能です。
すぐに結果を出せる
CBTはインターネットを活用してパソコンで行うため、採点や集計作業もスピーディに完了します。一方、従来の紙の試験では、解答用紙を回収したうえで1枚ずつ採点する必要がありました。その後に集計するため、結果をまとめるまでに長い時間がかかります。CBTなら試験の結果をすぐに確認でき、そのデータをタイムリーに活用しやすいです。
データの一元管理ができ詳細な分析が可能になる
CBTは解答をパソコンで行うため、結果をデータとして管理できます。解答のデータだけでなく、結果の集計も一元管理できて便利です。取りまとめたデータを活用し、詳細な分析も行えます。たとえば、特定の条件に基づいてデータを抽出したり、問題ごとの解答時間や正答率などを割り出したりすることも可能です。CBTなら試験に関する情報を素早く把握し、柔軟に活用できます。
出題の幅が広がる
CBTなら、従来の試験よりも出題できる内容の幅が広がります。紙の試験では、音声や動画による出題はできません。しかし、CBTなら、パソコンで問題を表示する際に音声や動画も簡単に取り入れられます。画面を操作しながら解答する問題も出題可能です。出題の表現の自由度が高くなるため、受験者の理解度をより詳しく測りやすくなります。
試験問題の流出や紛失のリスクを減らせる
紙で実施する試験の場合、問題用紙や解答用紙を印刷し、試験会場へ送付する必要があります。厳重な管理が前提となるものの、用紙を紛失したり、問題の内容が事前に流出したりするリスクはゼロではありません。
一方、CBTはインターネットを利用して問題に関するデータを送受信します。試験を実施するタイミングでリアルタイムなやり取りが可能です。CBTは安全性が高く、リスクを抑えて試験を実施できます。
受験者にとってのメリット
次に、受験者にとってのメリットを見ていきましょう。
試験会場や日時を自由に選択できる
CBTの試験会場は、受験者自身が自分で選べます。また、試験日も一定期間の中から選択可能です。従来は試験会場や試験日が限定されているケースが多く、忙しい人は都合がつかず受験を見送るケースもあったと考えられます。しかし、CBTなら試験会場や試験日の自由度が高く、自分の都合に合わせて試験を受けられます。従来の紙の試験方法からCBTに切り替えれば、受験者が増える可能性を期待できるでしょう。
結果がすぐにわかる
試験終了後、その場で合否が判定・通知されることが多いため、受験者はすぐに結果を知ることができ、次の準備に取りかかれます。
受験者と主催者に共通のメリット
受験者と主催者に共通のメリットもあります。
公平性が高まる
CBT試験の導入によって、人為的なミスや不正行為を低減することで、公平性が高まります。特に、コンピュータが自動で採点するため、採点者による主観や採点ミスが入り込む余地がありません。これにより、全ての受験者が同じ基準で評価されます。
CBT試験のデメリット
メリットが多いCBTにも、デメリットはあります。具体的にどのようなデメリットがあるか解説します。
パソコンが苦手な人は受験しにくい
CBTではパソコンを使用して試験を受けるため、受験者自身がパソコンを操作します。そのため、パソコンに慣れていない人や苦手意識のある人は、CBTをスムーズに受験できない可能性があります。
パソコンが不得意な人にもCBTを受けてもらうには、試験の流れや操作方法などを丁寧に説明しなければなりません。たとえば、動画を作成して手順を伝える方法があります。
通信/システム障害リスクがある
CBT試験は、ネットワークやシステムに依存しています。そのため、サーバーダウンや通信障害が発生した場合、試験が中断・中止されるリスクがあります。
主催者は、万が一の事態に備え、代替手段や対応フローを事前に準備しておく必要があります。
CBT試験に合わせたカンニング対策が必要
CBTは統一された環境で行われるため、PBT(紙の試験)に比べて不正対策がしやすいとされています。
しかし、以下のようなCBTならではの不正行為への対策も必要です。
試験問題の流出
受験者がスマートフォンなどで画面を撮影し、SNSなどで試験問題が流出するリスクがあります。
画面共有ソフトの利用
悪意のある受験者が、画面共有ソフトなどを使って遠隔地から指示を受ける可能性も考えられます。これらの対策として、試験会場での厳格な本人確認や持ち物チェック、監督官による巡回監視などが不可欠です。
1度に受験できる人数に上限がある
CBTはテストセンターのパソコンを使用するため、会場のキャパシティや空席状況によって1度に受験できる人数には上限があります。同じ日の同じ時間帯に受験の希望者が集中した場合、一部の人は別の日時でないと受験できない可能性があります。一般的には実施回数を増やし、年間で受験できる人数を調整することで対応可能です。
CBTが向いている試験
CBTはどのような試験に向いているのでしょうか。以下で具体的に解説します。

選択肢から正解を選ぶ試験
選択肢の中から正解を選んで解答する試験は、CBTへの切り替えがしやすいです。たとえば、計算問題は正しい答えが1つしかないため、CBTで選択肢を提示して解答してもらうとよいでしょう。
受験者・実施機会が多い試験
受験者の数や実施する回数が多い試験についても、CBTが向いています。CBTは受験の回数が多くても効率的に対応できるという特徴があります。採点や集計も素早く行えるため、負担を抑えてスムーズに試験を実施可能です。
CBT試験の今後
ICT環境の進化に加え、コロナ禍の影響によりCBTが普及しました。文部科学省もCBTのさらなる普及に取り組んでいます。ペーパーレス化の推進やSDGsをはじめとする環境問題への対策としても、CBTの選択は有効です。
CBTは時代に適した試験方式としての認識が増しており、今後はさらに普及すると考えられます。日常的にインターネットに触れている人が多いため、受験者もスムーズに対応できる可能性が高いです。
まとめ
CBTはパソコンやインターネットを活用する試験であり、近年は特に導入が進んでいます。採点や集計の手間も少なく、スムーズに試験を実施できます。CBTは、今後さらに一般的になっていくでしょう。
スマート入試は、堅牢な不正防止に優れたオンライン試験サービスです。パソコンやスマートフォンのカメラとAIを活用し、分かりづらい不正を素早く発見できます。企業や大学などさまざまなところで導入が進んでいるところです。インターネットを活用した試験を適切に行うために、ぜひ導入を検討してください。
資料請求
本ページの不明点を、下記のリンクからAIチャットボットに質問することができます↓
スマート入試ご案内ボット